外科のよくある疾患
- 外傷(切り傷・擦り傷・咬傷・挫傷、挫創・やけど、
犬や猫に噛まれた、山などで虫に刺されたなど) - 異物刺入(トゲや釘が刺さったときなど)
- 捻挫、打撲
- 皮膚のできもの
- 皮下腫瘤
- 痔の診療(切れ痔、いぼ痔など)
- けが、やけどの跡が治らない
- 手術やけがの跡が痛い
- 巻き爪、陥入爪
など
膿瘍(のうよう)
膿瘍(のうよう)とは?
膿瘍とは、皮膚や内臓などの組織内に膿が溜まってできる炎症のことを指します。膿は、白血球や細菌などが死滅した組織液と細菌から分泌される酵素が混ざり合ったもので、体のいたる部位で生じ得ます。また、皮膚膿瘍では発熱や悪寒など、感染症の症状が出ることもあります。
原因
膿瘍は、傷口から細菌が侵入して生じることが多く、けが以外では、肺炎や副鼻腔炎などの感染症も原因となります。細菌が体内に侵入すると、免疫系は感染と戦う白血球を患部に送り込みます。この白血球が細菌を攻撃すると、周囲の組織が損傷し、その部分に穴が開いてしまいます。その穴に膿がたまり、それが膿瘍と呼ばれるものになります。このほか、皮膚の炎症が慢性化することで、膿瘍ができることもあります。
治療方法
膿瘍の治療は、原因となった細菌を除去することが重要です。
軽度の場合、外科的治療によって治療が可能ですが、重症の場合は、外科的治療に加え抗生剤の投与が必要になります。
蜂窩織炎(ほうかしきえん)
蜂窩織炎(ほうかしきえん)とは?
蜂窩織炎とは、皮膚の下の組織が細菌感染によって炎症を起こし、赤く腫れた状態になる疾患です。
炎症部分に蜂の巣のような模様が現れることから、蜂窩織炎と呼ばれるようになりました。
原因
蜂窩織炎の原因は、一般的に細菌感染によるものです。細菌が傷口や虫刺されなどから侵入して炎症を引き起こします。また、糖尿病患者や免疫力が低下している人、リンパ浮腫の人などに発生しやすい傾向があります。
治療方法
蜂窩織炎の治療は、早期の発見が重要です。症状が悪化している場合には手術が必要になることもあります。蜂窩織炎では、主に炎症を抑えることを目的に治療します。
以下に代表的な治療法を紹介します。
- 抗生物質の投与:
蜂窩織炎の原因菌に合う抗生物質を内服することで、炎症を抑えます。投与期間は通常、7~14日間程度とされています。炎症が強い場合は、抗生剤の点滴を行うことがあります。
- 患部のドレナージ:
膿が溜まっている場合は、患部から膿を排出するためにドレナージ(穿刺排膿)を行います。患部の状態によっては、複数回に分けてドレナージを行うこともあります。 - 患部の冷却:
炎症が強い場合は、氷や冷水で患部を冷やすことで痛みを和らげることができます。 - 患肢の安静:
患肢を安静にし、軽く挙げることで炎症を鎮め、痛みを和らげます。
慢性不調
当院では、発熱をはじめとする風邪様症状には対応していません。
 アレルギー疾患や生活習慣病といった『慢性疾患』の診療に対応しております。
アレルギー疾患や生活習慣病といった『慢性疾患』の診療に対応しております。
また、体調不良で悩んでいるが何科に相談すればよいかわからず、困ったことがあるという方も少なくないかと思います。その際は、ひとまず当院にご相談いただければ、体調不良を起こしている原因が何かを突き止めて、最適な治療方針をご提案することができます。
なお、当院で治療が難しい疾患の疑いがある場合には、提携先の高度医療機関をご紹介しておりますので、どうぞご安心ください。
このような症状は当院へ
-
食欲不振、胸やけ
-
階段を上ると息が切れる
-
胸や背中に急激な痛みが起こった
-
胸痛が起こることがある
-
高血圧
-
動悸、胸の圧迫感
-
頭痛、頭がモヤモヤする
-
足のむくみ
-
発疹
-
のどがすぐに渇き、飲水量が増えた
-
尿の異常(近い、出にくい、血が混じる、量が多い)
-
便秘、下痢、異常な色の便
-
体重増加、減少
-
健康診断で異常があるといわれた
当院が対応する慢性不調
当院では、発熱をはじめとする風邪様症状には対応していません。
慢性疾患
アレルギー疾患(花粉症、アトピー性皮膚炎、気管支喘息)、生活習慣病(糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高血圧症、痛風(高尿酸血症)、メタボリック症候群など)、頭痛、貧血 、便秘症 など
生活習慣病の治療

糖尿病、脂質異常症(中性脂肪やコレステロールが高い状態)、高血圧、肥満、高尿酸血症(痛風)などが代表的な生活習慣病として知られており、食べ過ぎや運動不足といった不規則な生活習慣や不摂生などによって引き起こされます。生活習慣病は症状が軽くても、複合的に発症するおそれもあるため注意が必要です。また、生活習慣病が慢性化すると、脳卒中や心筋梗塞といった深刻な疾患を発症するリスクもあります。発症間もない段階では自覚症状がほとんどなく、体調に異変を感じて受診した時点ですでに重篤な状態となっていることも珍しくありません。日々の生活習慣を正して発症予防につなげていくようにしましょう。
当院では、生活習慣を見直すことから指導させていただきます。具体的には、食事療法(時間、内容、量)や運動療法のサポートを行い、必要に応じて薬物療法も行います。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠中に何度か呼吸が止まるまたは低呼吸状態になる疾患で、呼吸努力を伴う閉塞性睡眠時無呼吸症候群(Obstructive Sleep Apnea Syndrome:OSAS)と呼吸努力を伴わない中枢性睡眠時無呼吸症候群(Central Sleep Apnea Syndrome:CSAS)の2つに大別されます。そして圧倒的に多いのがOSASです。このOSASでは、空気の通り道である気道が物理的に塞がれることで、空気が出入りできなくなり呼吸が止まる、または空気の出入りする量が極端に少なくなって低換気状態になってしまいます。気道が物理的に塞がれる原因としては、肥満による首回りの脂肪蓄積、元々舌が大きいなどの解剖学的構造、緊張が緩むことによる舌根沈下、上気道の炎症や腫れ、睡眠中の姿勢などが挙げられます。なかでも肥満によるものが多く、男性によくみられます。
睡眠中に何度も呼吸が止まるため、熟睡できず、日中に強い睡魔に襲われるようになります。このため、仕事、学業、各種作業等のパフォーマンスが著しく低下するほか、交通事故、重機での事故など、命にかかわることにもつながりかねません。また、呼吸数が低下するため酸素が肺に十分に送られないことから、心疾患、高血圧、脳血管疾患、糖尿病のリスクが増大します。
新型コロナウイルス蔓延時、酸素飽和度を計測するサチュレーションモニターが注目されましたが、そのとき95%を下回るかどうかがある程度の基準として報じられていました。しかし、重度のOSAS患者さんでは、これが80%台、70%台まで一時的に落ち込むこともあります。また、診察時、医師を目の前にしながら眠りに落ちる方もいらっしゃるくらいです。このことから睡眠時無呼吸を放置することが、どれ程リスクが高いかということがわかります。
CPAP療法
 睡眠中に呼吸が止まっているのではないかという患者さんには、まず規定の検査を受けていただきます。一定の条件に該当する場合、保険診療でCPAPという治療を受けることができます。
睡眠中に呼吸が止まっているのではないかという患者さんには、まず規定の検査を受けていただきます。一定の条件に該当する場合、保険診療でCPAPという治療を受けることができます。
CPAPとは、持続陽圧呼吸(Continuous Positive Airway Pressure)療法の略で、専用の医療機器を用いて気道に持続的に圧力をかけて気道を広げ、空気が出入りする経路を確保する治療法のことです。専用のCPAP機器には呼吸回路と呼ばれるチューブが取り付けられており、これに特殊なマスクを接続します。この特殊なマスクを鼻に装着して本体の電源を入れると鼻の中に空気が流れ込んできて、気道が持続的に広げられます。睡眠中、ずっとこの鼻マスクを装着したまま呼吸をしてもらいます。使用期間中は、呼吸回路とマスクを洗って乾かすというお手入れが必要になりますが、熟睡できるようになることを考えればそれも苦にならないとおっしゃる方がほとんどです。
また、この療法が登場した当時は、機器の性能が満足できないものが多かったですが、最近のものはかなり優秀になっており、ほとんど不快なく睡眠できるのではないかと思います。
次の症状がある方は睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。
- いびきをよくかく
- 途中でよく目が覚める
- 睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された
- 夜間の頻尿
- 寝汗がひどい
- むせて目が覚める
- なかなか起きられない
- 起床時、口が渇いている、頭痛がある
- 日中、強い眠気に襲われる
- だるい、倦怠感がある
- 集中力がない
上記の症状がある方は、当院にご相談ください。規定の検査の結果に基づいて、CPAP療法、温存療法などを行います。
また、原因が体重過多の場合は食事療法や運動療法も平行してご提案いたします。
不定愁訴のお悩みにも対応しております。
少し体調が悪いくらいでわざわざ医師に相談するのはおっくうに感じる方も多いかと思います。しかし、体調不良を感じたらなるべく早めに専門医に相談することで、さまざまな疾患の早期発見と進行予防につながるとされています。
詳しい症状や不調を感じる部位がはっきりわかっている方は、専門の診療科に相談することをお勧めします。相談すべき診療科がわからない方は、ひとまず当院にご相談ください。その際、治療可能なケースもあれば、しかるべき診療科におつなぎすることもあります。
体調不良を感じたときにすぐに相談できるかかりつけ医を見つけておくのが理想です。まずは遠慮なく当院までご相談ください。
整形外科
 整形外科は運動器外科とも呼ばれ、立つ、座る、歩く、走るといった動作を行う運動器官である骨、筋肉、関節、靭帯、軟骨、神経などに関する外傷や疾患を診療しております。
整形外科は運動器外科とも呼ばれ、立つ、座る、歩く、走るといった動作を行う運動器官である骨、筋肉、関節、靭帯、軟骨、神経などに関する外傷や疾患を診療しております。
運動機能が低下すると、日常生活にも支障をきたし、QOL(生活の質)の低下を招くおそれもあります。生活習慣を見直して発症予防や進行防止に努めましょう。
私たちにとってありふれた症状である腰痛、肩こり、手足のしびれ、膝痛、神経痛などに留まらず、四肢の捻挫、打撲、骨折といった外傷の診療も行っております。
また、交通事故などによる首や腰などの痛みにも対応しています。交通事故にあった当初は、無症状や軽症でも、時間が経ってから症状が出るおそれもあるため注意が必要です。
麻酔科・ペイン
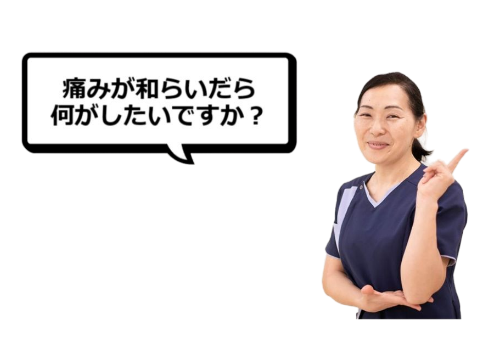 ペインクリニックは、痛みに対する治療を専門的かつ包括的に行う診療科です。
ペインクリニックは、痛みに対する治療を専門的かつ包括的に行う診療科です。
ただ痛みがあるからといって直ちにペインクリニックで対応するのではなく、必要に応じて原因疾患を専門的に対応する診療科と連携しながら診療にあたります。
当院では、痛み止め薬や湿布、各種注射などの西洋医学だけでなく、漢方を併用したハイブリッド治療で痛みの緩和効果を高めて治療を行っています。
当院で対応できる治療
ペインクリニックでは、神経ブロック療法を行うことが可能です。
これは、局所麻酔薬を神経に直接もしくは神経の周辺に投与して少しの間だけ痛みを緩和させることで、私たちが本来持っている回復力を促進させるものです。また抗炎症薬を併用することで、痛みを引き起こす箇所の炎症を緩和させます。これにはさまざまな種類があり、神経の種類によって使い分けます。
ブロック注射
ブロック注射とは
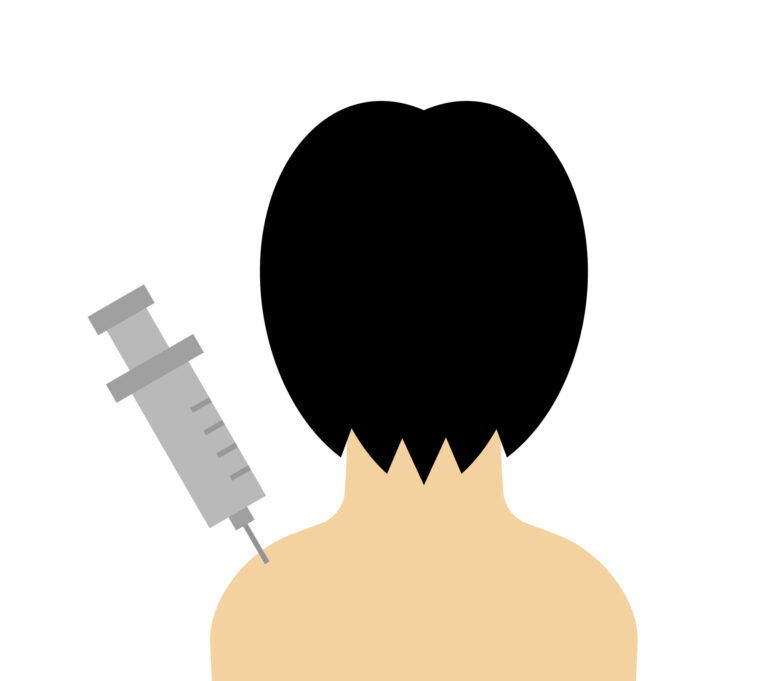 ブロック注射とは、痛みが生じている場所の神経や筋肉に麻酔薬を投与することで痛みを解消するものです。外来にて保険適用で受けていただけます。 顔・首・肩・手足・腰・膝などの全身の痛み、突発性難聴、帯状疱疹の痛み、顔面神経麻痺などに効果があるとされています。
ブロック注射とは、痛みが生じている場所の神経や筋肉に麻酔薬を投与することで痛みを解消するものです。外来にて保険適用で受けていただけます。 顔・首・肩・手足・腰・膝などの全身の痛み、突発性難聴、帯状疱疹の痛み、顔面神経麻痺などに効果があるとされています。
こんなお悩みの解消にお勧めできます
- 服用中の薬が効かない
- 貼り薬や塗り薬が効かない
- マッサージや電気治療の効果がない
- 今すぐに痛みを解消したい
- 痛みを解消するため手術を提案されたが、休暇を長期間取れない
- 手術後の痛みや違和感がなかなか消えない
など
ブロック注射の種類
トリガーポイント注射
トリガーポイントとは痛みとこりがある場合にみられる圧痛点のことで、局所麻酔薬を投与することで、血流促進、痛みの解消、筋肉の緊張緩和が期待され、体内で痛みを引き起こす物質を取り除くことにつながります。
神経ブロック注射(仙骨硬膜外、坐骨神経、肋間神経)
神経ブロック注射は、ステロイドや局所麻酔薬を神経周囲に注入する治療法です。この注射によって、神経やその周辺で発生する炎症、痛み、興奮が抑制され、痛みの緩和が図られます。また、血流を改善し、筋肉の緊張を和らげる効果もあります。内服薬とは異なり、便秘やふらつき、眠気など全身性の副作用もほとんど起こらないとされています。
1度のブロック注射だけで効果が現れる方もいらっしゃいますが、週1回の注射を4〜5回継続する方やそれ以上継続する方もいらっしゃいます。 感染、神経損傷、出血などを併発するおそれがありますが、経験豊富な医師が治療を行いますのでぜひ一度ご相談ください。
全身にブロック注射が可能です
顔も含め全身のあらゆる神経にブロック注射が可能です。詳しくは以下をご参照ください。
| 顔 | 眼神経ブロック、下顎神経ブロック |
|---|---|
| 肩 | 肩甲上神経ブロック |
| 胸 | 肋間神経ブロック |
| 腰 | 仙骨硬膜外ブロック、仙腸関節ブロック |
| 臀部・下肢 | 梨状筋ブロック、外側大腿皮神経ブロック、大腿神経ブロック、脛骨神経ブロック、坐骨神経ブロック |
治療する神経に応じて、針を刺す場所、薬の量などに違いがありますので、複数の疾患があっても同じ神経を治療する場合は同じブロック注射が効果を発揮します。具体的には、椎間板ヘルニアと帯状疱疹の治療の際に、同じ神経を治療する場合にはブロック注射も同じものとなります。
効果のある痛み・病気
以下のような疾患・痛みに有効とされています。
- 頭痛(片頭痛・群発頭痛・緊張型頭痛など)
- 複合性局所疼痛症候群(CRPS)
- 腰痛症
- 三叉神経痛
- 口腔顔面痛
- 頚椎症・ストレートネック・スマホ首
- 顎関節症
- 帯状疱疹後神経痛
- 坐骨神経痛
- 頚肩腕症候群
- 筋膜性疼痛症候群(首こり、肩こり、腰痛)
- 肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)
- 椎間板ヘルニア(頚椎・腰椎)
- 脊柱管狭窄症(頚部・腰部)
- 四肢血行障害
- 内臓の病気(がん、腫瘍、婦人科疾患等、消化器系疾患、腎疾患など)
- 変形性関節症
- 関節リウマチ
なお、保険診療のブロック・トリガーポイント注射でも痛みの軽減がみられない場合には、自費診療で「キントン」による注射も行っております。保険診療の注射にはキシロカインやステロイドが含まれているため、妊婦さんや授乳中の方で赤ちゃんのことを最優先にしたい方、またはこれらの成分にアレルギーのある方など、ご要望があればお知らせください。
ブロック注射の流れ
ブロック注射にはさまざまな種類があり、トリガーポイント注射、肋間神経ブロック注射、仙腸関節ブロック注射、肩甲背神経ブロック注射、仙骨ブロック注射、硬膜外ブロック注射など、それぞれ治療の進め方は異なりますが、基本的な治療の進め方については以下をご参照ください。
1初診
ご来院の際に問診表を記入していただきます。
お薬手帳、保険証、お持ちの方は紹介状(診療情報提供書)、他院撮影の画像などもご提出をお願いいたします。
2検査と診療
問診表の内容を基に、医師より診察を行い、状況次第で血液検査やレントゲン検査を実施します。
診察が終わってから、ブロック注射の適応が認められれば、治療方針を丁寧にご案内し、理解していただけましたら治療に移ります。
3安静
注射後、待合室やベッドでしばらくの間休憩していただきます。治療内容によっては、20〜60分程度の休憩をお願いすることもあります。
4医師と効果判定
お話を聞いたうえで、治療効果をチェックします。
今後の治療の進め方をご案内し、帰宅していただきます。
ご来院~ご帰宅まで、治療内容次第ですが初診の方は1〜2時間程度、再診の方は30分〜1時間程度を見込んでおります。
その他の治療
以下のような治療も選択肢としてあります。
薬物療法
痛み止めの処方が中心です。痛み止めにはさまざまな種類があり、ご本人の状況に応じて最適な処方を行います。
痛み止め、鎮痛補助薬、外用剤(湿布、塗り薬)だけでなく、特に漢方(保険適用)を積極的に併用する点が当院の特徴です。
物理療法
痛みが生じる部位の血流を促したり、筋肉の緊張を緩めたりするために、温熱療法、マッサージなどを実施します。
ワクチン
ワクチンの料金
| ワクチン名 | 接種料金(税込み) |
|---|---|
| インフルエンザ | 3,850円 |
※初診料が必要な医療機関が多いなか、当院では自費診療について初診料はいただいておりません。
開始時期については当ホームページにてお知らせします。
インフルエンザワクチン
毎年秋頃から季節性のインフルエンザが流行しはじめます。インフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルスに感染しても発症するリスクを抑えることができるとされています。
国内で供給されているワクチンは、特殊な処理によって病原体が不活化されているため安全性が高く、副作用も比較的少ないため小児から高齢者まで幅広い年齢層の方に受けていただけます。
ただし、このワクチンは培養の過程で鶏卵を使っています。卵にアレルギーがある方は注意が必要です。13歳以上では1回(1回でも2回分の抗体価が得られる)、13歳未満では2回接種するのが基本とされています。
インフルエンザワクチンに関するデータ
・国内のワクチンは4価ワクチンと呼ばれるA型株(H1N1株+H3N2株)とB型株(山形系統株+ビクトリア系統株)が含まれている。
・有効性について、65歳以上のデータでは、発病の阻止率34~55%、死亡阻止率82%との報告がある。また、2015年-2016年の6歳未満のデータでは、有効率60%とのデータもある一方で、乳幼児に関しては報告によってその率が20~60%と幅があり、ワクチン接種のみならず日常生活で感染を予防するための各種対策を講じる必要がある*1。
・高齢者では、心臓疾患、脳血管疾患、肺炎、インフルエンザによる入院のリスクが減少するほか、死亡リスクも低下する[1]。
・体がインフルエンザウイルスと十分に戦える状態になるのが接種から約4週間後とされているため、その時期を考慮して接種を受けるようにする。厚生労働省は、おおむね12月の中旬までに受けるのを推奨している。
・インフルエンザワクチン接種は医療費控除の対象外。
参考までに米国のインフルエンザワクチン有効率をみてみると、全年齢層での有効率は2021-2022年で36%(A型)でした*2。
参考元
*1 厚生労働省発表のデータによる(令和4年度インフルエンザQ&A (mhlw.go.jp))
*2 米国疾病対策センター(CDC)発表のデータによる(Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness, 2021-2022 (cdc.gov))
[1] Nichol KL, Nordin J, Mullooly J, Lask R, Fillbrandt K, Iwane M. Influenza vaccination and reduction in hospitalizations for cardiac disease and stroke among the elderly. N Engl J Med. 2003 Apr 3;348(14):1322-32. doi: 10.1056/NEJMoa025028. PMID: 12672859.
ワクチン接種の流れ
- インフルエンザワクチンを希望される方はこのホームページのWEB予約画面または電話にて、予約をお取りください。
- 来院したら問診票と同意書に記入していただきます。
- 診察後、接種します。
- 会計が済んだら終了です。
がんのセカンドオピニオン
セカンドオピニオンとは、治療方針や診断内容について、かかりつけ医以外の複数の専門医からも意見を聞くことで、最良の治療法を選択できるようにすることです。ご自身が納得できる治療法を選択することは、患者さんの当然の権利です。リスク、他の選択肢などについて把握したうえで、最良の選択ができるようにお手伝いいたします。
セカンドオピニオンの流れ
セカンドオピニオンを受けるためには、最初にかかりつけ医に相談のうえ、診療情報提供書(紹介状)を作成していただくようにしてください。病状の推移や治療経過を適切に理解することで、正しいアドバイスができるようになります。そのため、主治医からの紹介状(診療情報提供書)、検査結果(レントゲン写真・放射線画像フィルム・病理標本・検査データ等)などを準備していただきます。
また、セカンドオピニオンを最大限活用するために、相談当日までに疑問点や質問事項を整理しておくことをお勧めします。
ご自身の病気に関する一般的な情報を収集する
経験者のお話、WEB検索などで、ご自身の病気についてできるだけ多くの情報を収集しましょう。
ただし、集めた情報をすべて真に受けるのは止めましょう。ご自身で情報の取捨選択ができない場合は、お気軽にご相談ください。
質問内容、ご自身の病気の経過について整理しておく
かかりつけ医から聞いたお話のほか、ご自身が迷っている点や疑問点などを自分の言葉で伝えられるようにしておくことで、セカンドオピニオンの相談がスムーズに進みます。
費用
| 料金(税込み) |
|---|
| 最初の30分 5,500円 |
| 延長15分ごとに 3,300円 |

 当院では、10時間にも及ぶことがある食道癌など、難易度の高い大手術をいくつもこなしてきた女性医師が、
当院では、10時間にも及ぶことがある食道癌など、難易度の高い大手術をいくつもこなしてきた女性医師が、